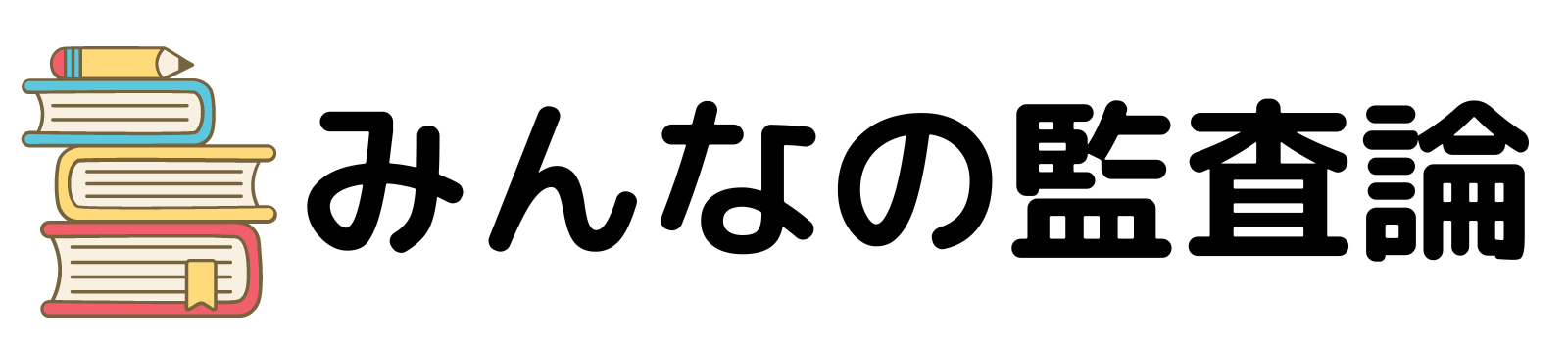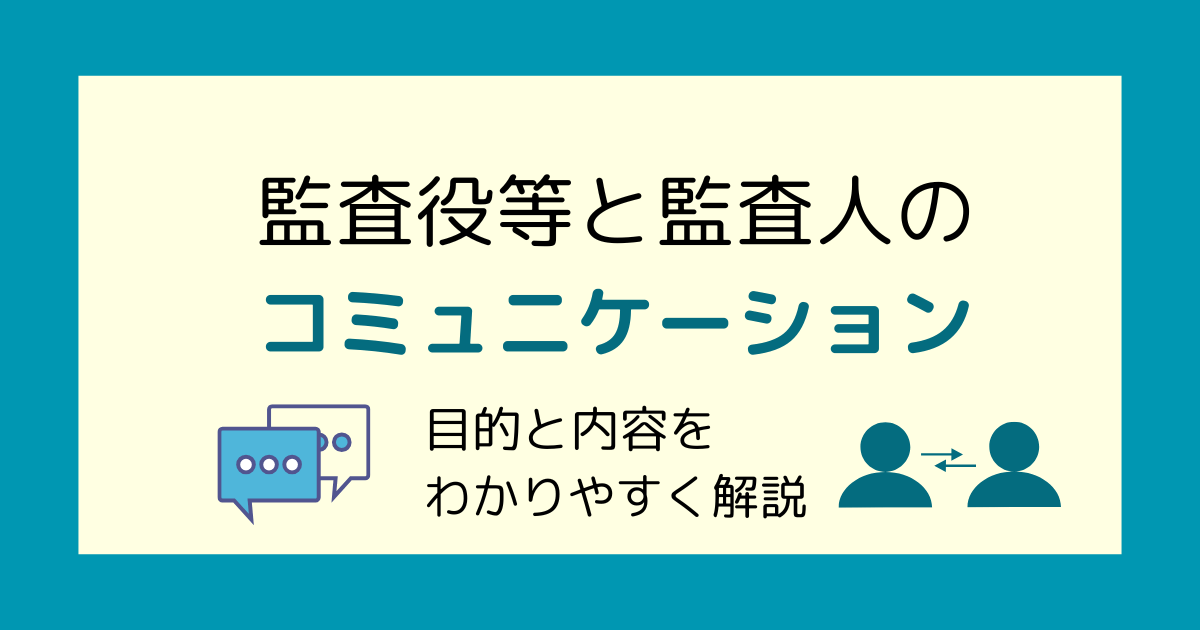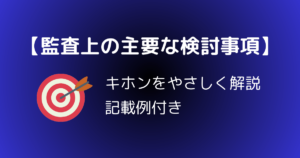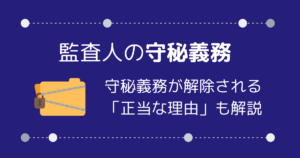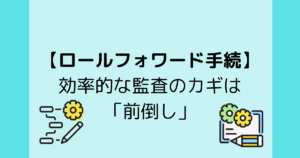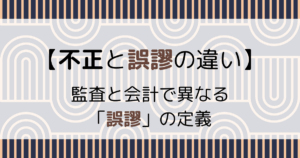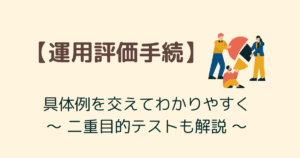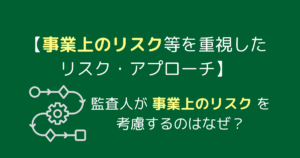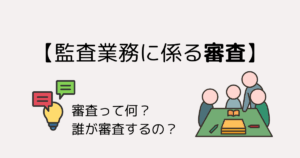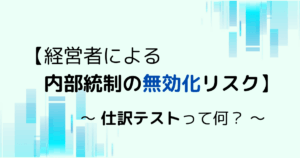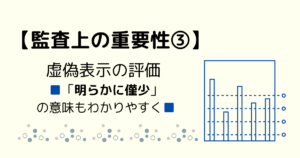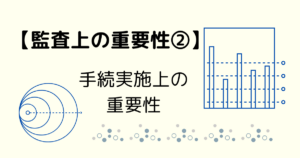きみが本を読んでいるなんて珍しいな。…「雑談力を高める本」?



監査人になったら、監査役等とコミュニケーションをとらなくちゃいけんでしょ。今のうちに雑談力を磨こうと思って。



監査役等とのコミュニケーションには、雑談力はさほど必要ないと思うけど…。それより、コミュニケーションの目的や内容を覚えるのが先だよ。
監査役等(監査役若しくは監査役会又は監査委員会、監査等委員会)と監査人は、相互に連携し、双方向のコミュニケーションを行うことが求められています。
この記事では、公認会計士 のそのそ が、監査役等と監査人のコミュニケーションの目的とその内容をわかりやすく説明します。
- 監査役等と監査人のコミュニケーションの目的
- 監査役等と監査人のコミュニケーションの内容
- 監査役等と監査人のコミュニケーションの方法
監査役等と監査人とのコミュニケーションに関する法律上の規定



ここでは、会計監査人設置会社である上場会社の監査を想定するね。



つまり、会社法に基づく会計監査人監査と金融商品取引法に基づく監査の両方の対象となる会社だね。



本題に入る前に…、
監査役等と監査人のコミュニケーションに関連して、会社法と金融商品取引法にどんな規定があるか、確認しておこう。
会社法における関連規定
監査役等は、業務監査と会計監査を行うものとされています。



ただし、会計監査人設置会社の場合、監査役等の会計監査は、「会計監査人による会計監査が適正に行われているかどうか」を検討することによって行うという建て付けになっているよ。
監査役等による監査報告には、
・会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは,その旨及びその理由
・会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関する事項
を含めるものとされています(会社計算規則127条)。
つまり、監査役等は、会計監査人による会計監査が適正に実施されているかどうかを検討することを通じて、会計監査を行うことになります。



このしくみのためには、監査役等と監査人との間で緊密なコミュニケーションが行われる必要があるね。
なお、会計監査人は、取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく監査役に報告しなければなりません。監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができます(会社法397条)。
さらに、会計監査人の選任・解任などの議案内容の決定権は、監査役等にあります(会社法344条、399条の2、404条)。



これらの規定も踏まえれば、監査役等と監査人がコミュニケーションを行うことは不可欠なんだ。
金融商品取引法における関連規定
一方、金融商品取引法は、監査人が、会社における法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実(「法令違反等事実」)を発見したときは、事実の内容及び事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、遅滞なく、会社に対して書面で通知するものと定めています(金融商品取引法193条の3)。
この通知は、監査役等が受けるものとされています(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令7条)。



金融商品取引法も、監査役等と監査人がコミュニケーションを行うことを想定していると言えそうだね。



法令違反等事実への対応についての詳細は、また今度説明するね。
監査役等と監査人とのコミュニケーションに関する監査基準の規定



前置きはこれにくらいにして、監査基準の規定を確認しよう。



ここまで前置きだったの!?
監査基準 第三 実施基準 一 基本原則
7 監査人は、監査の各段階において、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)と協議する等適切な連携を図らなければならない。
監査人と監査役等との連携に関する上記の規定は、平成25年監査基準改訂の際に明示されたものです。



平成25年には「監査における不正リスク対応基準」が設定されたよ。
この「不正リスク対応基準」では、不正リスクの内容や程度に応じ、監査人が適切に監査役等と協議する等、監査役等と連携を図らなければならない旨が規定されたんだけれど、当時の監査基準には監査役等との連携に関する規定がなかったんだ。
財務諸表監査において監査役等との連携が重要であることは、不正が疑われる場合に限定されません。そこで、監査基準においても、監査人が、監査の各段階において,適切に監査役等と協議する等、監査役等と連携を図らなければならないことが明記されました。



「不正リスク対応基準」は、別の機会に勉強しよう。
監査役等と監査人とのコミュニケーションの効果



さて、いよいよ本題に入れるぞ!



まだ本題に入っていなかったの!?



監査人が監査役等とコミュニケーションをすることは、財務諸表監査においてどんな意味を持つと思う?



監査役等も監査をしているわけだから…
監査人が監査役等とコミュニケーションをすれば、監査役等からいろんな情報を得ることができるはずだよね。
監査役等が日常の業務監査を通じて得た情報を監査人に伝えることで、監査人は、さまざまな情報を入手することができます。


また、監査人が財務諸表監査に係る事項や財務諸表監査を通じて得た情報を監査役等に伝えると、監査役等が財務報告プロセスを監視するという自らの役割を一層適切に果たすことができ、内部統制の有効性を高めることに間接的に寄与します。結果として、会社の統制リスクが低い水準となり、重要な虚偽表示リスクが低減されると考えられます。


すなわち、監査人と監査役等が「双方向」でコミュニケーションを行うことで、財務諸表監査の有効性及び効率性を高める効果が期待されているのです。



監査人が一方的に質問して、監査役等がそれに答えるというわけではなくて、キャッチボールのように情報をやり取りするんだね。



そのとおりだよ。
双方向のコミュニケーションを行うことで、監査役等が行う監査の有効性や効率性にも寄与するね。
監査役等と監査人のコミュニケーションの内容



コミュニケーションすべき事項はある程度定められているよ。
監査人が監査役等とコミュニケーションを行う事項は、次のとおりです。
- 財務諸表監査に関連する監査人の責任
- 計画した監査の範囲とその実施時期(識別した特別な検討を必要とするリスクの内容を含む)
- 監査上の重要な発見事項
・企業の会計実務の質的側面のうち重要なものについての監査人の見解
・監査期間中に困難な状況に直面した場合、その状況
・監査の過程で発見され,経営者と協議したか又は経営者に伝達した重要な事項
・監査人が要請した経営者確認書の草案
・監査報告書の様式及び内容に影響を及ぼす状況
・財務報告プロセスに対する監査役等による監視にとって重要と監査人が判断したその他の事項 - 監査人の独立性
- 品質管理のシステムの整備・運用状況(公認会計士法上の大会社等に対する監査などの場合)



こんなに多くの事項についてコミュニケーションするんじゃ、雑談する暇はないか…。



コミュニケーションの内容からわかると思うけれど、どこかのタイミングで年に1回だけコミュニケーションの機会を設けるというわけではなくて、年間を通じてコミュニケーションを重ねていくよ。



雑談力より日程調整力が必要そうだ。



ちなみに、「②計画した監査の範囲とその実施時期」についてコミュニケーションを行う際には、監査の有効性を損なわないような配慮が必要だよ。



監査計画を事前に伝えて監査人の手の内を明かすわけだから、状況によっては、その伝え方を工夫する必要があるということだね。
また、上場企業の場合には、「④監査人の独立性」についてのコミュニケーションに関して、
・独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨
・独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項(監査対象期間に関連した報酬金額を含む)
・識別した独立性に対する阻害要因が許容可能な水準にないと判断する場合、その阻害要因を生じさせている状況を除去する対応策又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために適用されるセーフガード
も(追加で)コミュニケーションするものとされています。



倫理規則(職業倫理に関する規定)の詳細は、ここでは省略するけれど、上場企業に対する監査は社会的影響が大きいから、監査人の独立性に関して詳細なコミュニケーションが要求されているよ。
なお、会社法は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関する事項を、会計監査人が監査役等に通知することを求めており(会社計算規則131条)、「⑤品質管理のシステムの整備・運用状況」に関するコミュニケーションはこれを兼ねると解されます。
このコミュニケーションには、規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容、監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果が含まれます。



上記のほかにも、監査人が監査の過程で内部統制の重要な不備を識別した場合、それに関するコミュニケーションを行うよ。
内部統制の不備に関するコミュニケーションは、別の機会に勉強しよう。
監査役等と監査人とのコミュニケーションの方法



コミュニケーションは具体的にどんな方法で行うの?
居酒屋でコミュニケーションするのはダメだろうけど。
監査人と監査役等のコミュニケーションは、双方が集まる報告会の開催や書面(又は電磁的記録)によるほか、協議などの簡略的な方法で行うこともあります。リモート会議でコミュニケーションを行うこともあります。



つまり、基本的には、口頭もしくは書面(又は電磁的記録)でコミュニケーションを行うよ。
ただし、次の項目については、書面(又は電磁的記録)によるコミュニケーションを行わなければなりません。
・監査上の重要な発見事項について、監査人が口頭によるコミュニケーションが適切ではないと考える場合
・上場企業の場合における、監査人の独立性に関する事項(上記の④)
・品質管理のシステムの整備・運用状況に関する事項(上記の⑤)



重要な事項については、きちんと書面として残すということだね。



つまらない雑談が書面に残されなくてよかった。
監査上の主要な検討事項との関係



最後に、両者のコミュニケーションと、「監査上の主要な検討事項(KAM)」との関係を整理しておこう。



「監査上の主要な検討事項」は平成30年の監査基準改訂で導入されたんだったね。
監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った事項を決定した上で、その中からさらに、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項を「監査上の主要な検討事項」として決定しなければなりません。



「監査上の主要な検討事項」は、監査役等とのコミュニケーションを前提として決定されるものなんだね。



そうだよ。
「監査上の主要な検討事項」の導入によって、監査役等と監査人との連携に本質的な変化が生じたわけではないけれど、年間を通じて、より一層密接なコミュニケーションが求められるようになったと言えるね。
「監査上の主要な検討事項」に関して監査人と監査役等が継続的なコミュニケーションを行うことは、監査役等が、財務報告プロセスを監視するという自らの役割を一層適切に果たすことにもつながります。
また、「監査上の主要な検討事項」が監査報告書で報告されることを踏まえ、状況によっては、その事項に関連する追加的な情報の開示を監査役等から経営者に促すことが期待されています。



監査報告書における「監査上の主要な検討事項」の記載と、会社による開示の関係については、監査人の「守秘義務」を説明した際にも取り上げたよ。
◆まとめ◆
・監査人と監査役等が双方向でコミュニケーションを行うと、①監査人が監査役等から情報を入手できるとともに、②監査役等が財務報告プロセスを監視する責任をより適切に果たすことができ、重要な虚偽表示リスクの低減につながる。
・コミュニケーションの内容は、計画した監査の範囲と実施時期、監査上の重要な発見事項、監査人の独立性など多岐にわたる。
・一定の事項については、書面(又は電磁的記録)によるコミュニケーションが必須とされる。



僕たちのコミュニケーションには致命的な問題点がある!
きみが一方的に説明してばかりで、双方向のコミュニケーションになっていないよ!



…その指摘は重要だから、書面に残しておこう。



監査役を務める人はもちろん、経理部門や法務部門の人にもおすすめ。
「曲突徙薪」は、災いが起こるのを未然に防ぐことのたとえ。漢文ってかっこいい!