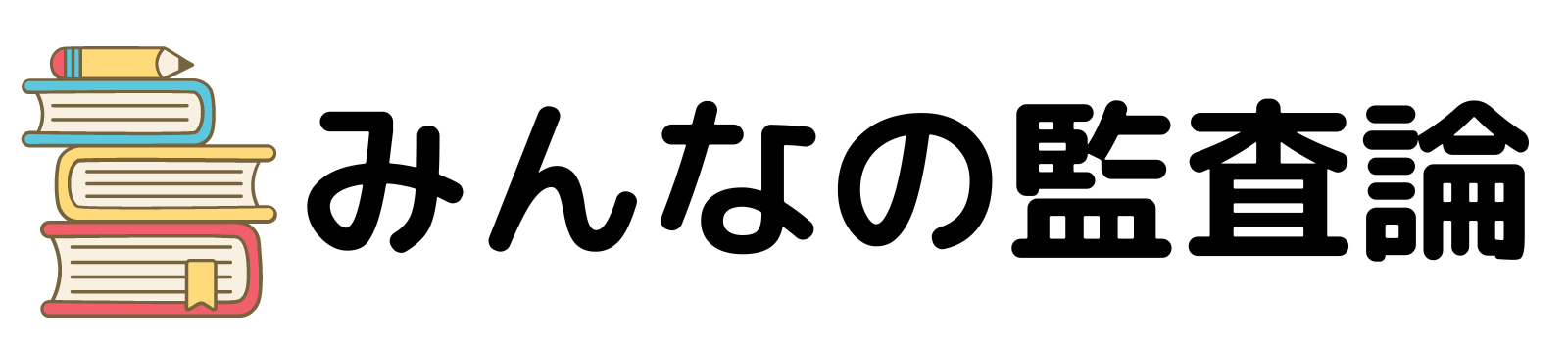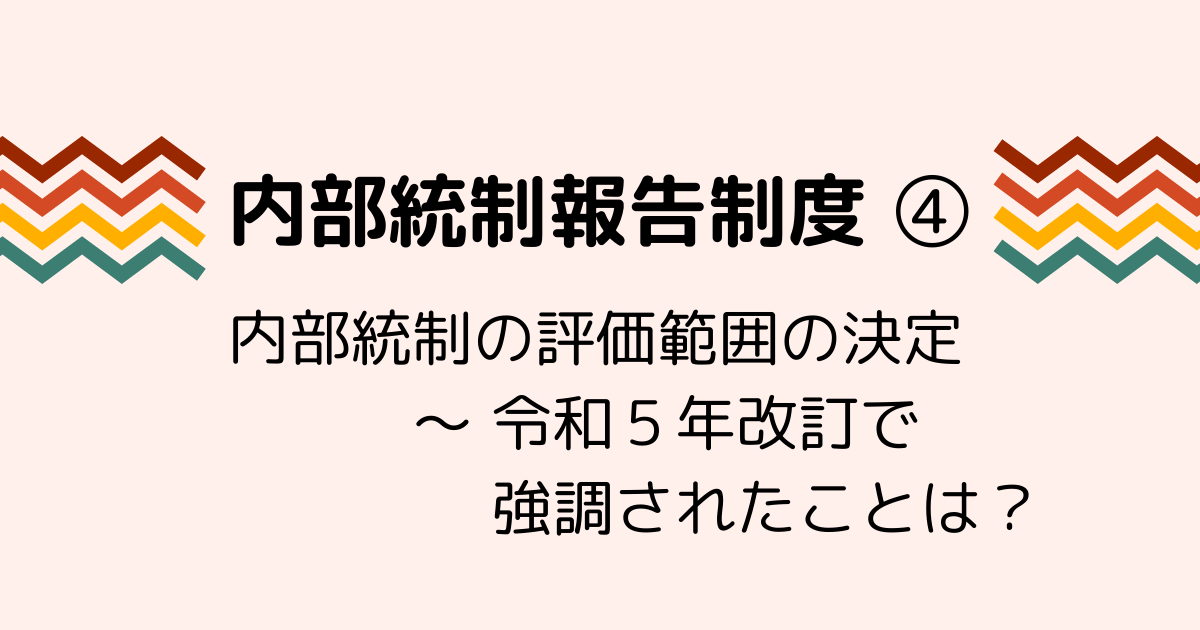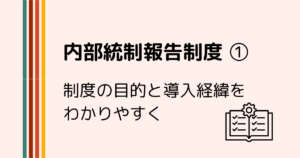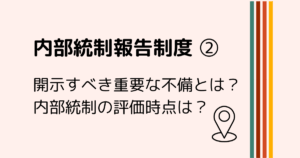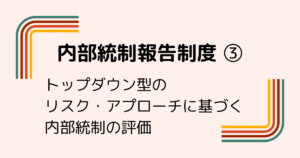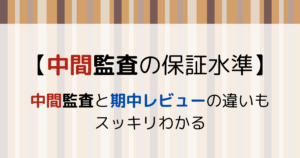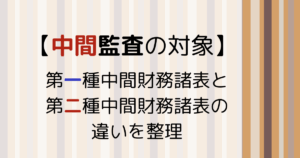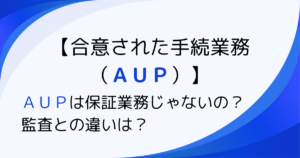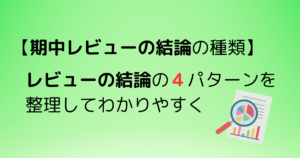電車でディズニーランドに行ったんだけど、帰り道の東京駅の乗り換えでくたびれた。



東京駅で京葉線から他路線に乗り換えるには、同じ駅とは思えない距離を歩くからね。



乗換案内アプリで検索した結果が、そのルートだったのに。



帰り道は疲れているから、検索結果だけを機械的に適用すると痛い目にあう。
特定の判断基準を「機械的に適用すべきではない」ことは、内部統制実施基準にも書いてあるよ。
我が国では、金融商品取引法により、上場会社等を対象に、財務報告に係る内部統制の経営者による評価と公認会計士等による監査が義務づけられています。
内部統制基準・内部統制実施基準が令和5年に改訂された際、経営者による内部統制の評価範囲の決定に関し、例示される量的基準や項目などを機械的に適用して判断すべきでないことが強調されました。
この記事では、公認会計士 のそのそ が、内部統制報告制度における内部統制の評価範囲の決定手順と、これに関する令和5年改訂の概要をわかりやすく解説します。
- 内部統制の評価範囲の決定手順
- 評価範囲の決定に関する令和5年改訂の概要
トップダウン型のリスク・アプローチに基づく内部統制の評価
我が国では、金融商品取引法により、上場会社等に内部統制報告書の提出が義務付けられています。
上場会社等の経営者は、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、その評価結果を示した内部統制報告書を作成し開示しなければなりません。
この内部統制報告制度では「トップダウン型のリスク・アプローチ」に基づく評価が採用されています。
トップダウン型のリスク・アプローチ:内部統制の評価にあたり、まず連結ベースで全社的な内部統制の評価を行い、その結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価を行うしくみ



まずは全社的な内部統制が有効に機能しているかどうかについて心証を得て、それに基づいて、財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着眼して、業務プロセスに係る内部統制を評価するんだよね。



トップダウン型のリスク・アプローチの概要は、この記事で解説しているよ。
内部統制の評価範囲の決定



内部統制の評価範囲は具体的にどう決定するの?



大まかな手順はこの図のようになるよ。
順番に説明するね。
内部統制の評価範囲の決定手順
| Ⅰ 全社的な内部統制の評価 |
| ▼ |
| Ⅱ 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定 |
| ⑴ 決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定 |
| ⑵ 決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定 |
| ① 重要な事業拠点の選定 |
| ② 評価対象とする業務プロセスの識別 |
全社的な内部統制の評価



まずは、全社的な内部統制について評価するんだよね。
全社的な内部統制については、原則として、全ての事業拠点について全社的な観点で評価します。
ただし、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについては、その重要性を勘案して評価対象としないこともできます。例えば、売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は、僅少なものとして評価の対象から外すといった取扱いが考えられます。



重要性が僅少という判断は、経営者が、必要に応じて監査人と協議して行うものだよ。この比率をそのまま機械的に適用すればよいというわけではないことに注意!
財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点の判断は、例えば、売上高の一定比率といった基準を全ての連結子会社に適用するのではなく、各連結子会社の事業の内容などに応じ、異なる基準を適用する方法も考えられます。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定



全社的な内部統制の評価を行った結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を決定するんだよね。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を決定するにあたっては、業務プロセスを次の2つに大別して考えます。
- 決算・財務報告プロセス
- 決算・財務報告プロセス以外の業務プロセス
決算・財務報告プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定
決算・財務報告プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものは、全社的な内部統制に準じて、全ての事業拠点について全社的な観点で評価します。
全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスとしては、例えば、次のような手続が挙げられます。
・総勘定元帳から財務諸表を作成する手続
・連結修正、報告書の結合及び組替など連結財務諸表作成のための仕訳とその内容を記録する手続
・財務諸表に関連する開示事項を記載するための手続



財務諸表に直結するこうした決算・財務報告プロセスは、全ての事業拠点について全社的な観点で評価する必要があるんだ。
ただし、決算・財務報告プロセスも、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについては、その重要性を勘案して評価対象としないことも認められます。
決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の決定
決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスについては、次の手順で評価範囲を決定します。
【①重要な事業拠点の選定】
まず、評価対象とする事業拠点を、売上高等の重要性により決定します。
事業拠点を選定する指標としては、基本的には売上高が用いられますが、企業の置かれた環境や事業の特性によって、総資産、税引前利益などの異なる指標や追加的な指標を用いることもあります。



銀行なら、経常収益という指標を用いることが考えられるね。
各事業拠点について、指標の金額の高い拠点から合算していき、連結ベースの一定割合に達している事業拠点を評価対象とすることが考えられます。
この一定割合は、企業によって異なります。ただし、全社的な内部統制の評価が良好であれば、たとえば、連結ベースの売上高のおおむね3分の2程度とする考え方があります。



売上高を指標とした場合の「3分の2」という割合は、あくまでも例に過ぎないよ。この割合を機械的に適用するわけではないことに注意しよう!
ただし、次の要件を全て満たす場合は、その事業拠点を当年度の評価対象としないことも認められます。
- その事業拠点が前年度に重要な事業拠点として評価範囲に入っていた
- 前年度のその事業拠点に係る内部統制の評価結果が有効であった
- その事業拠点の内部統制の整備状況に重要な変更がない
- 重要な事業拠点の中でも、特に重要な事業拠点でない(グループ内での中核会社ではない)



この取扱いによれば、評価範囲をさらに絞り込むことができるね。



そうだよ。
この取扱いをする場合は、前述の一定割合(例えば売上高の3分の2)を結果として下回ることもあり得るよ。
なお、全社的な内部統制のうち良好でない項目がある場合は、それに関連する事業拠点は評価範囲に含める必要があります。
【②評価対象とする業務プロセスの識別】
選定した重要な事業拠点における、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスは、原則として、全てを評価対象とします。
「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」は、一般的な事業会社であれば、例えば、原則として、売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定が考えられます。



しつこいけど…、
「売上・売掛金・棚卸資産の3勘定」もあくまで例示だよ。業種や事業の特性などに応じて、適切に判断する必要があるんだ。
たとえば銀行なら、預金・貸出金・有価証券の3勘定に至る業務プロセスを、原則的な評価対象とすることが考えられるね。
なお、その重要な事業拠点が行う重要な事業又は業務との関連性が低く、財務報告に対する影響の重要性も僅少である業務プロセスについては、評価対象としないことも認められます。例えば、売上を「企業の事業目的に大きく関わる勘定科目」とする場合に、売上に至る業務プロセスの金額を合算しても連結売上高のおおむね5%程度以下となる業務プロセスは、評価の対象から外すといった取扱いが考えられます。



繰り返しになるけど…



しつこいよ!5%を機械的に適用するのはダメってことでしょ。



おっしゃる通りです。
なお、棚卸資産に至る業務プロセスには、販売プロセスのほか、在庫管理プロセス、期末の棚卸プロセス、購入プロセス、原価計算プロセスなどが関連すると考えられますが、これらのうちどこまでを評価対象とするかについては、企業の特性などを踏まえて、虚偽記載の発生するリスクが的確に捉えられるよう、適切に判断される必要があります。一般に、原価計算プロセスについては、期末の在庫評価に必要な範囲を評価対象とすれば足りると考えられるので、必ずしも原価計算プロセスの全工程にわたる評価を実施する必要はありません。



この手順で評価範囲を決定するのが基本だけれど、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスが他にもあるなら、個別に評価対象に追加するんだ。
選定された重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点において、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスは、個別に評価対象に追加します。
個別に評価対象に追加する業務プロセスとしては、次のようなものが挙げられます。
・リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス
・見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス
・非定型・不規則な取引など虚偽記載が発生するリスクが高いものとして、特に留意すべき業務プロセス
そして、全社的な内部統制の評価結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲・方法等を調整します。



全社的な内部統制の評価結果が有効でない場合には、その影響を受ける業務プロセスに係る内部統制について、評価範囲の拡大や評価手続を追加するなどの措置が必要だね。



全社的な内部統制の評価結果が有効である場合は、業務プロセスに係る内部統制の評価に際して、サンプリングの範囲を縮小するなど簡易な評価手続を取ったり、評価範囲の一部について一定の複数会計期間ごとに評価の対象としたりすることが考えられるよ。
評価範囲を決定する際の留意点
評価範囲を決定するにあたっては、長期間にわたり評価範囲外としてきた特定の事業拠点や業務プロセスについて、評価範囲に含めることの必要性の有無を考慮しなければなりません。



前述の手順で評価範囲を決定すると、長期にわたって評価範囲外とされる事業拠点や業務プロセスが存在することも考えられるね。そうしたところで不正などが起こる可能性もあるから、それも考慮したうえで評価範囲を決定すべきということだよ。
また、評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスにおいて開示すべき重要な不備が識別された場合には、その事業拠点又は業務プロセスについては、少なくともその開示すべき重要な不備が識別された時点を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切とされています。



評価範囲の外で開示すべき重要な不備が識別されたなら、それは評価範囲に追加する必要があるんだね。



これらの点は、令和5年の改訂で明示されたよ。
具体例



評価範囲の決定手順を、数値例を使って復習しよう。
【具体例】
・P社の連結売上高に対する各事業拠点の売上高の割合は次の通りである。
P社:40% S1社:23% S2社:19% S3社:10% S4社:8%
・重要な事業拠点を選定する際に用いる指標は売上高とし、一定割合は3分の2とする。
・企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高・売掛金・棚卸資産とする。
・前年度はP社・S1社を重要な事業拠点として選定しており、いずれも評価結果は有効だった。
・当年度において内部統制の整備状況に重要な変更はない。
・P社グループの中核会社はP社である。
全社的な内部統制:
P社・S1社・S2社・S3社・S4社の全てについて全社的な観点で評価する。
※最も小さいS4社も5%超なので、財務報告に対する影響の重要性が僅少とは言えない。
決算・財務報告プロセス:
全社的な観点で評価することが適切と考えられるものは、P社・S1社・S2社・S3社・S4社の全てについて全社的な観点で評価する。
決算・財務報告プロセス以外の業務プロセス:
①重要な事業拠点の選定
P社のみ 40% →3分の2(≒66.6…%)を超えない
P社+S1社 (40%+23%=)63% →まだ3分の2を超えない
P社+S1社+S2社 (40%+23%+19%=)82% →ここで3分の2を超える
原則としては、P社・S1社・S2社を重要な事業拠点として選定する。
ただし、S1社は、前述の要件を全て満たすので、当年度は評価対象としないこともできる。
※P社はグループの中核会社であり特に重要な事業拠点に該当するため、評価対象とする必要がある。S2社は、前年度は重要な事業拠点として選定されておらず評価対象に入っていなかったため、評価対象とする必要がある。
②評価対象とする業務プロセスの識別
①で選定した事業拠点の、売上高・売掛金・棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象とする。
選定された重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠点において、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスがあるなら、個別に評価対象に追加する。
内部統制基準・内部統制実施基準の令和5年改訂の概要
「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、内部統制基準・内部統制実施基準)は令和5年に改訂されています。



令和5年の改訂前も、経営者による評価範囲の決定は、前述と同様の手順で行われていたよ。でも、実務において、経営者による内部統制の評価範囲の外で開示すべき重要な不備が明らかになる事例もみられたんだ。



評価範囲に含めていないところで問題があったということは、そもそもの評価範囲の決定があまりうまくいっていなかったのかなあ。



一概には言えないけれど、経営者が内部統制の評価範囲を決定するにあたって、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか、と懸念されたんだ。
前述の手順で挙げた「売上高のおおむね3分の2」や「売上・売掛金・棚卸資産の3勘定」などは、あくまでも例なんだけれど、経営者がこれを機械的に適用して評価範囲を決定しているのではないかと指摘されたんだよ。
こうした指摘を踏まえ、令和5年における内部統制基準・内部統制実施基準の改訂により、内部統制の評価範囲の決定に関し、例示される量的基準や項目などを機械的に適用して判断すべきでないことが強調されています。



令和5年改訂前文では、この点が次のように説明されているよ。一読しておこう。
一 経 緯
(前段省略)…一方で、経営者による内部統制の評価範囲の外で開示すべき重要な不備が明らかになる事例や内部統制の有効性の評価が訂正される際に十分な理由の開示がない事例が一定程度見受けられており、経営者が内部統制の評価範囲の検討に当たって財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮していないのではないか等の内部統制報告制度の実効性に関する懸念が指摘されている。(途中省略)
二 主な改訂点とその考え方
(2) 財務報告に係る内部統制の評価及び報告
① 経営者による内部統制の評価範囲の決定
経営者が内部統制の評価範囲を決定するに当たって、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮すべきことを改めて強調するため、評価範囲の検討における留意点を明確化した。具体的には、評価対象とする重要な事業拠点や業務プロセスを選定する指標について、例示されている「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきでないことを記載した。
また、評価範囲に含まれない期間の長さを適切に考慮するとともに、開示すべき重要な不備が識別された場合には、当該開示すべき重要な不備が識別された時点を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切であることを明確化した。評価対象に追加すべき業務プロセスについては、検討に当たって留意すべき業務プロセスの例示等を追加した。(以下省略)



「売上高等のおおむね3分の2」などの量的基準や、「売上・売掛金・棚卸資産の3勘定」の例示があることで、実務において内部統制報告制度が効率的・安定的に運用されていた面はあっただろうね。
ただ、それらを機械的に適用しすぎて、制度の本質が見落とされることがないように、あくまでも例示であることが強調されたんだね。



財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮して評価範囲を決定することが大切なんだね。
◆まとめ◆
・全社的な内部統制は、原則として全ての事業拠点について全社的な観点で評価する。
・決算・財務報告プロセスのうち全社的な観点で評価することが適切なものも、全ての事業拠点について全社的な観点で評価する。
・決算・財務報告プロセス以外の業務プロセスについては、重要な事業拠点を選定し、その重要な事業拠点における、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスを、原則として全て評価対象とする。それ以外にも、重要性の大きい業務プロセスは個別に評価対象に追加する。
・上記手順に関しては、量的基準や項目が例示されるが、それを機械的に適用すべきではない。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を適切に考慮して評価範囲を決定する必要がある。



ところで…、
ディズニーランドに行くのに、そもそも電車に乗る必要はないのでは?ぼくたち、飛べるんだから。



そうか!乗換案内アプリに「飛ぶ」っていう検索結果がなかった!



検索結果を機械的に適用するから、そういうことになるんだよ。



しつこいぞ。



勘定科目や証憑などに生じる”異常点”の見つけ方と対応策が具体的に解説されているよ。監査にも活用できるし、経理部門や内部監査部門の方にもおすすめ。